
地方の会計事務所の強みを最大化。お客さまに寄り添い必要とされる存在へ。
税理士法人 宮田会計
代表社員 宮田 健一郎
石川県生まれ。新潟大学大学院卒業。
2005年 アクタス税理士法人入社。
2010年 税理士法人 宮田会計入社。
2016年 代表社員就任。
※所属や役職、記事内の内容は取材時点のものです。
海外留学と東京での5年間の修業を経て、家業を継ぐため帰郷。
宮田会計は1962年に私の祖父が創設し、60年以上の歴史を持つ会計事務所です。祖父は私が小学生の頃に他界し、婿養子で入った私の父が税理士の資格を取って家業を継ぎました。父は仕事と勉強を両立して40代で税理士に合格しましたが、幼少期はその姿を見て「大変そうな仕事だな」と漠然と感じていました。
税理士という職業がどんなものなのか、あまり把握しないまま大学は経済学部に進み、就職活動では東京で働くことを希望していました。しかし、私の時代は就職超氷河期と言われていた頃で、希望する企業の内定がなかなか出ませんでした。
そこでゼミの先生に相談したところ、「実家が会計事務所だから、大学院であと2年間学ぶ間に税理士の資格を取ったらどうか」とアドバイスをもらい、在学中に税理士資格を取得。その後はオーストラリアとニュージーランドに1年間の留学をしました。
もともと海外の仕事に携わりたいという考えがあり、将来的にその仕事内容に近い会計事務所への就職も視野に入れた事前準備のような形での留学でした。
帰国後に再び就職活動を行い、国際税務を手がけている東京のアクタス税理士法人に入社しました。そこでは5年ほど働き、上場企業やその関連会社の会計監査業務や当時世の中に出始めていた不動産証券化の案件などを担当しました。
入社当時は40名弱だった組織が退職時には180名にまで成長していて、勢いある組織の成長を間近で見られた貴重な機会だったと思います。その後、妻との結婚を機に30歳で石川県へ戻ることを決め、家業を継ぐことにしました。
地方のつながりを活かし、税理士法人の枠を超えた取り組みを開始。
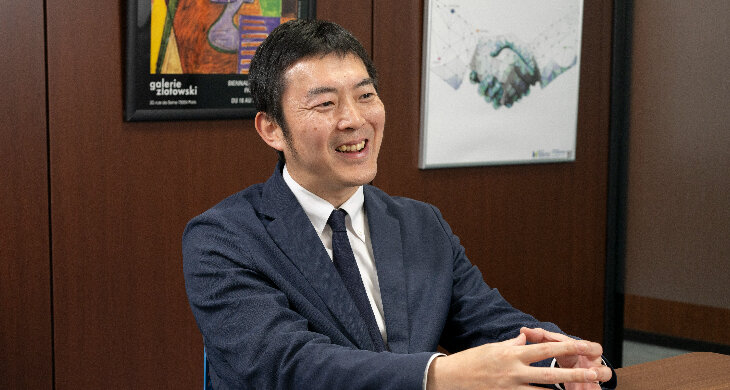
東京から地元に戻ったとき私が懸念していたのは、「仕事の進め方や考え方が異なるかもしれない」という点です。しかし、それは良い意味で予想と違いました。
家業では東京以上にシステマティックに仕事が進んでおり、職員の知識も豊富で驚きました。また、半分以上が私を幼少期から知る職員たちで、非常に好意的な雰囲気があったこともありがたかったです。
私が東京でやっていた仕事効率化やデジタル化の手法を取り入れた際も、皆すんなりと受け入れてくれました。このことは事務所が大きく変わるきっかけになったと感じています。
当時の宮田会計は農業分野に特化した部署を持っており、農家さんの支援に力を注いでいました。もともとは、「農家は土地を多く所有する資産家」という考えで農家の法人化や相続手続きを見込んだものと聞いています。現在では、石川県内の農業法人のうち6割が私たちとお付き合いがあります。
農家の跡継ぎである30代を集めて勉強会を実施したり、大手コンビニチェーンと農家さんの縁をつないで販路開拓を支援したこともあります。その頃から、徐々に「普通の会計事務所として留まるのではなく、お客さまのニーズに幅広く応えながら、宮田会計じゃなければと思ってもらえることをやろう」と考え始めました。
お客さまの「全部やってほしい」に応える、宮田会計ならではの強み。
私たちならではの取り組みの一つに、「お客さまの給与計算や労務を含め、会社の総務経理部門のすべてお引き受けする」というものがあります。一般的に多いのは、お客さま自身で帳簿を作って日々の経理業務を行い、会計事務所が監査するスタイルです。しかし、お客さまの負荷が大きいので本音では「全部やってほしい」と思っていることがわかりました。
私たちが経理業務を1から10まで担えれば、お客さまの困りごともすぐに察知できますし、いろいろなアドバイスができるので、ワンストップ対応に力を入れてきました。
もちろん、最初はオーソドックスな帳簿を作ることから始めました。しっかりと精度の高い帳簿を作れる基盤がある上で、プラスアルファで「宮田会計でないと」という特徴としてワンストップ化を徐々に推し進めていきました。
私が地元に戻った頃の宮田会計は、25名ほどの組織でした。地元で後継者がいない会計事務所の業務を引き継いだり、新しい人材を雇用して規模を拡大したりすることで、今では60名ほどの事務所となっています。地域との密なネットワークがあり、同業他社から「ぜひうちの事務所を引き継いでほしい」と言っていただけるのは非常にありがたいと感じます。
「おせっかい」が強い武器になる!宮田会計の採用基準。

宮田会計が求める仲間は、お客さまの立場になって親身に相談に乗れる方です。なぜなら、お客さまは必ずしも税理士という専門職を求めているのではなく、「自分のことや家族のこと、会社のことをしっかり理解したうえで、そこに寄り添ったアドバイスをしてくれる人」に担当になってほしいと思っているからです。
私たちの事務所の方針としては、お客さまについてきちんと把握することはもちろん、何か悩みがあったら税務会計に限らず何でも聞くことを大切にしています。
悩みごとを話題に出してくれるのはありがたいことですから、それに全力で応対する。単純にコミュニケーション能力が高いだけでなく、お客さまに寄り添える人材を私たちは必要としています。
ですから、面接でもこちらの質問に対して一所懸命に偽りない言葉で答えているかどうかを重視します。それがお客さまへの応対にそのまま表れるからです。
私は、おせっかい好きな人はとても宮田会計の仕事が合うと思います。お客さまの発言について自分なりに調べ、「調べたところ、こんな情報がありました」と報告できる。そんな真摯な姿は必ず信頼関係につながります。目の前の相手に真剣に向き合う人が、お客さまのニーズとしても高いと感じています。
異業種からの転職者も多く活躍。想いが仕事になる職場。
私が宮田会計に入社した15年ほど前と比べ、職員がおよそ倍の60名にまで増えましたが、そのほとんどが中途採用によるものです。中途採用の良さは、なんといっても前職での経験を活かしながらお客さまの懐に深く入り込めること。金融機関やハウスメーカー、不動産業界、税務署や市役所出身者といった幅広い人材が活躍しています。
それから、大手レストランチェーンで調理員として働いていた職員もいます。なぜ宮田会計に来たのかを聞いたら、「厨房に定期的に送られてくる箱に、いつも同じ量・サイズの野菜が入っていて、どうして同じものが届けられるのか不思議に思った。農業を支援する仕事に興味を持ったので」と話してくれました。
現在、その職員は能登地区の農業支援の中心メンバーとして活躍しています。「こんな仕事がしたい」という強い目的意識や想いがあれば、人はどこでも活躍できることを体現している例だといえるでしょう。
必ずしも税理士や会計の資格が必要なわけではなく、人が好きな方や、やってみたい仕事が宮田会計にある方はぜひ門を叩いてほしいです。
税理士事務所のネットワークで地域の未来を支えたい。

少子高齢化が叫ばれる昨今ですが、北陸3県の税理士の平均年齢は「62.3歳(2024年3月時点/北陸税理士会事務局調べ)」となっています。
平均年齢が60歳を超えている中で、後継者がおらず「お客さまも職員も抱えているのに、自分はいつまで事務所をやれるのか。誰に相談したらいいのかわからない」という方が、私たちを頼って事務所の統合へと至っています。
ただ現実問題、私たちがすべてのお客さまや会計事務所を救えるわけではありません。宮田会計としては、私たちの特色である農業支援・社会福祉法人・特殊法人、そして市町や公共団体といった会計を中心としながらも、事務所から距離が離れているお客さまは私たちとつながりのある税理士にカバーしてもらうような、幅広いネットワークを構築したいと考えています。
地域のお客さまが元気でないと、私たちも継続したサービスの提供は難しくなってしまうでしょう。いかにお客さまの手間を省きながら、地元企業を元気にし、地域活性化につなげるか。ここが今後の私たちの課題であり、重要な役割なのではないかと考えています。
地方ならではの人と人とのつながりを大切にしながら、一つひとつ丁寧に仕事をするのが宮田会計のモットーです。今後もますますお客さまとの信頼関係を深め、地域も経済もよくする税理士事務所として躍進を続けます。

